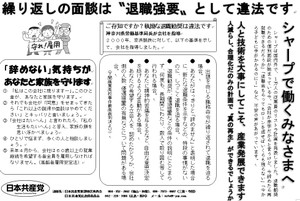福山市政に対する予算要望書を提出しました
本日、福山市長に対し、「2013年度福山市政に対する要求書」を市議団で提出をしました。
約15分ほどの市長との対談でした。
★村井あけみ市議「中学校給食の実現を。子どもたちが栄養のある給食をたっぷり食べられ、食育や問題行動軽減にもなるので、ぜひ取り組みを」
市長「もし行うとしたら、センター方式。今後の課題だと思っている」
★高木たけし市議は「学校の耐震化を急いでほしい。国の補助金制度もあるので有効活用を」
市長「危険な崩落するような箇所も行っていきたい。その地域に応じた耐震対策をすすめるべきではないか、と思っている」
★土屋とものり市議
「物づくりの街として、子供が興味をもち、手に触って確かめられるような、科学館などの創設は」
市長「作品の展示や、大学や企業とのコラボレーションを行うなど、夢はある」
★河村ひろ子市議
「市道からの水路への転落死亡事故対策を。今年度でも3名の方が亡くなっている。地域とも連携し、危険個所対策を」
市長「通学の安全点検は行っているが再度行い、その他も安全対策を進めていくよう予算もつける」
直接市長と直接面談をする機会は少ないのですが、有意義な時間となりました。
市民立場での予算編成となっているのか、今後議会の中で明らかにしていき、市議団一丸となって頑張ります!