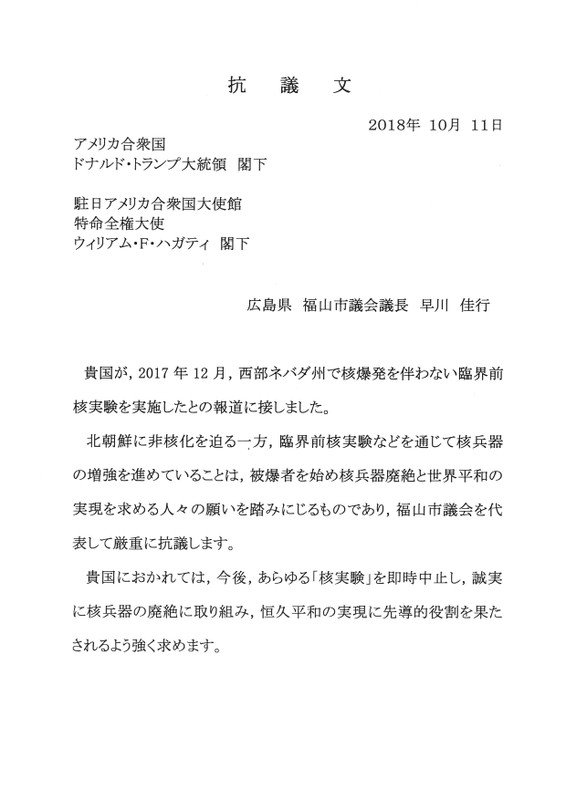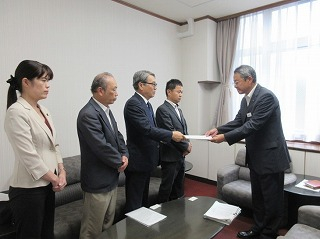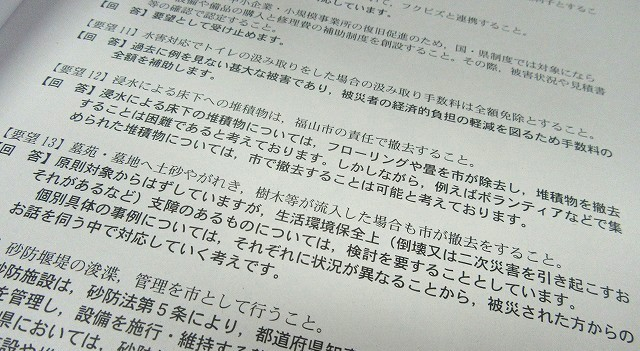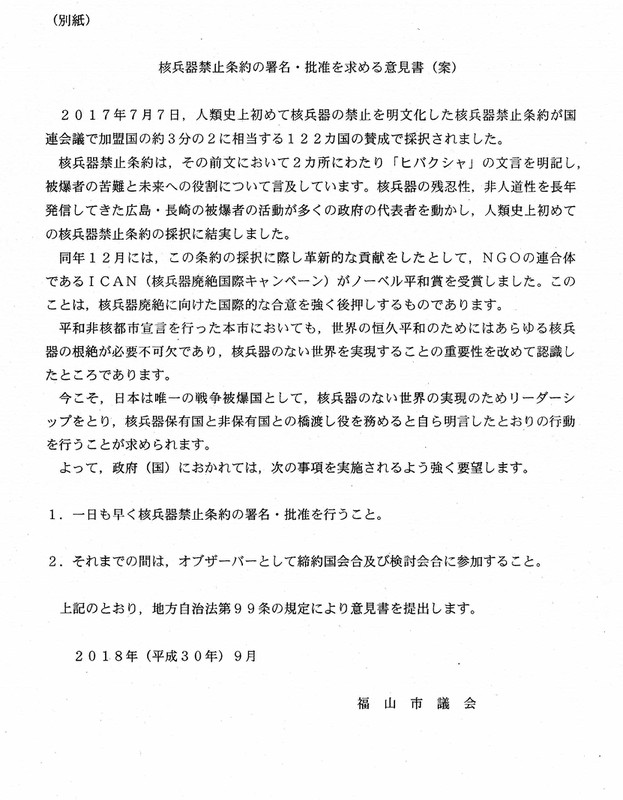介護・国保・後期高齢者医療―基金のためこみやめて、市民の負担を軽くせよ(2017年度福山市決算)
福山市決算委員会が10月9日から15日まで開かれ、2017年度の一般・特別会計を審議しました。
日本共産党市議団からは、村井あけみ、土屋とものり両市議が出席しました。
決算委員会は、福山市の予算の使い方とその結果などをチェックする場です。
介護など11の特別会計について、日本共産党の討論のおもな内容をご報告します。
介護保険料
滞納理由の62%は「生活困難」
介護保険料(65歳以上)は、毎年の引き上げが続いており、前年度比212円増の6万8633円(1人あたり)となりました。
滞納者は2059人で、そのうち62%にあたる1270人は「生活困難」が理由であることが分かりました。保険料負担が、高齢者の生活を圧迫しています。
保険料減免は、わずか15%
しかし、保険料が減免されたのは、わずか191人(15%)です。
減免制度の周知など、高齢者に寄り添った対応が行われているとは言えません。
周知と制度の拡充を抜本的に進めるよう求めました。
介護利用料も負担増
高額介護サービス費の月額負担上限は、3万7200円から4万4400円に引き上げられ、利用者の負担は大きくなっています。
基金残高は15億円も
一方で、介護給付費準備基金残高は15億3096万円に達しました。基金を使い、保険料・利用料を引き下げるよう求め、決算認定に反対しました。
後期高齢者医療
加入者の負担増の一方、収支は黒字に
後期高齢者医療保険料は6万7860円(1人あたり)で、前年度比1651円(2.5%)もの負担増です。
所得の低い人の軽減措置が縮小され、9084人が約8100円(1人あたり)の負担増となりました。
保険料の滞納は、553件にのぼります。
一方で、単年度収支は前年度3.3倍の1億7275万円の黒字となりました。
負担増を押しつけながら、黒字を増やすあり方は認められないと主張しました。
国民健康保険
1人あたりの保険税額は8万9835円で、前年度比394円の増でした。
保険税を払えず、資格証明書などを発行された世帯は6146世帯に上ります。
一方、単年度収支は21億9966万円の黒字で、6億9781万円を基金に積み立てました。
基金をためこむのではなく、払える保険税にするよう、引き下げを強く求めました。
他には
特別会計は他に、都市開発、集落排水、食肉センター、駐車場、商業施設、母子父子寡婦福祉資金貸付、誠之奨学資金、財産区と計11の事業会計があります。
賛成したもの、改善の要望をして賛成討論をしたもの、問題点の指摘や改善を求め反対討論をしたものがそれぞれあります。
討論を下記に掲載します。