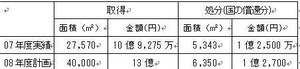2008/7/4 第54回福山市母親大会に参加しました
党市議団は、6月29日に開かれた福山市母親大会に参加しました。母親大会は今年で54回目を迎える歴史の長い運動です。会場の市中央公民館は約五百人の参加者で熱気にあふれていました。
午前は、五つの分科会にそれぞれ参加し、みなさんとともに子育て、教育、暮らし、食、平和などについて意見を出し合い、思いや悩みを語り合いました。
ちひろ美術館東京副館長の松本由理子さんが講演
--------------------------------------------------------------------------------
午後からは、ちひろ美術館東京副館長の松本由理子さんが「いわさきちひろの絵本と人生」と題して講演。松本さんは、岩崎ちひろの人生を深く写し出す絵、ちひろが余命をかけて描いた「戦火の中の子どもたち」の絵に込められた願いなどの絵のすばらしさを語りました。参加者は、涙ぐみ、笑いながら講演に聞き入り、「帰って、ちひろの絵本を読み返したい」「勇気をもらいました」と話していました。
大会は最後に、「平和憲法を守り、世界の人々と共に、平和の道を歩み続け、核も基地もない地球を、子どもたちに手渡すために共に力をあわせましょう」と呼びかけるアピールを満場の拍手で確認しました。
母親大会の歴史
--------------------------------------------------------------------------------
1954年、アメリカの水爆実験でマグロ漁船員の久保山愛吉さんが「死の灰」を浴びて亡くなりました。広島・長崎につぐ三度目の被爆に母親たちは「原水爆なくせ」の署名運動に立ち上がり、全国に広げました。
1955年日本の母親の声は平塚らいてうさんたちによって国際民主婦人連盟に届けられ「原水爆から子どもを守ろう」と世界母親大会の開催が決まりました。それに先立ち6月、第一回日本母親大会が東京で開かれ、日本各地の炭鉱や農村からも、一円募金などで送り出された2000人の母親たちが集まりました。
以来今日まで、全国各地で毎年大会を開かれつづけ、”母親が変われば社会が変わる”と母親・女性の願い実現のためにねばりづよく運動をすすめています。
生命を生みだす母親は 生命を育て 生命を守ることをのぞみます
--------------------------------------------------------------------------------
大会のスローガンは「生命を生みだす母親は 生命を育て 生命を守ることをのぞみます」です。これは世界母親大会に寄せられたギリシャの詩人・ペリディス夫人の詩の一節ですが、これはすべての母親・女性の心をとらえ、連帯のスローガンになっています。
このスローガンを中心に母親大会は、母親・女性の願い、子どもたちのしあわせのために、思想・信条を越えていろいろな立場の女性たちが一堂に集まり、みんなで知恵をよせあい励ましあい、明日に生きる勇気をつちかう集いとなっています。