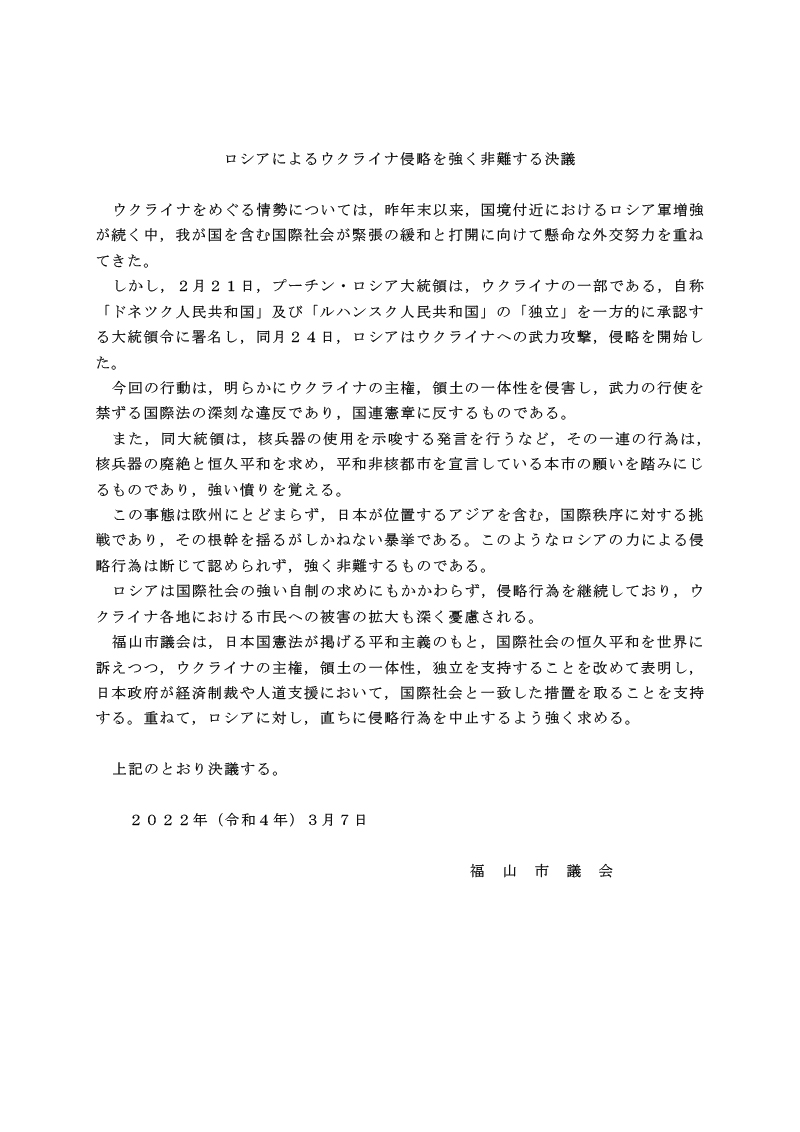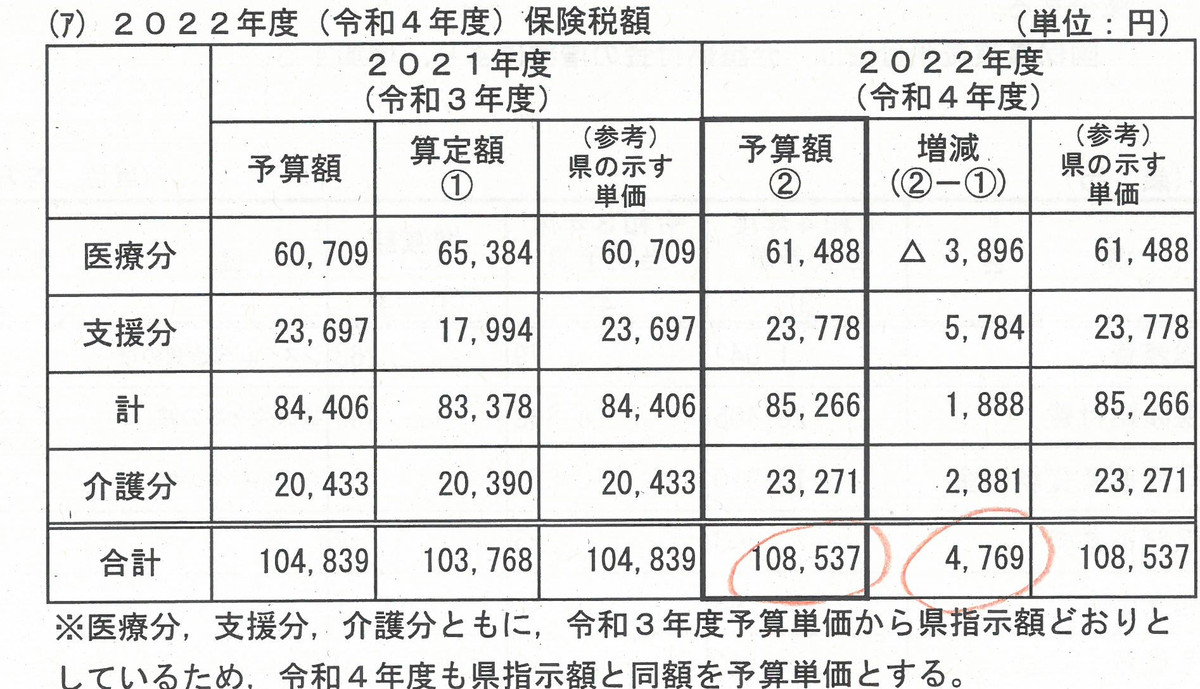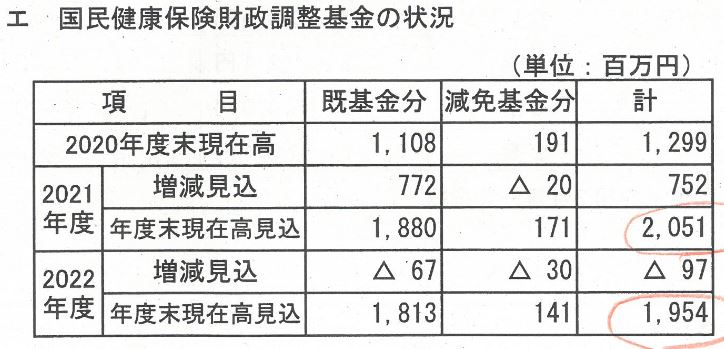学校統廃合やめよ―子どもの意見を尊重せよ(2022年3月議会報告)
福山市は今年度末、小中学校11校を廃止します。
コロナ禍で学級・学年閉鎖が相次ぐ中、新校舎も完成しないのに7校を統廃合するなど、非常に乱暴です。
日本共産党の河村ひろ子市議は、子どもや保護者、住民に十分な説明もせず、合意も得ないまま統廃合を進める市教育委員会の強引なやり方に強く抗議することを改めて表明し、相手を尊重しない三好雅章教育長に反省を求めました。
子どもの権利条約にもとづく意見表明権を
3月に廃止される学校に通う子どもの「とても寂しく悲しい」との手紙を河村市議が読み上げた時、他の議員から「子どもをダシにするな」とヤジが飛びました。
子どもの意見を代弁し、その権利を守ることも議員の役割です。軽んじるようなヤジは許せません。
日本共産党市議団は、学校統廃合計画が出された当初から、「子どもの権利条約にもとづく意見表明権を保障し、子どもの意見を聞け」と求めてきました。
「誰も、私たちがどうしたいか聞いてくれなかった」この子どもの声にこたえる責任が、行政や議会には求められます。

今回、廃止される学校。以前、見学に伺ったときの写真です。
小規模な複式学級で、子どもも先生も生き生きと授業をしていました。