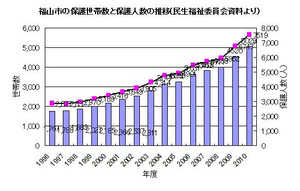2011/6/17 特別支援教育の充実求める
特別支援教育の充実を
障害のある子どもの教育条件の改善を
日本ではいま、障害のある子どもたちの教育のために、①特別支援学校(障害児学校)②小中学校の特別支援学級(障害児学級)③通級指導教室(通常の学級から週1回程度通う)という、主に3つの特別な場が設けられています。ここ数年、こうした場で学ぶ子どもたちの数は急増しています。
体制不足は政治の責任
今の特別支援教育体制は、2007年に、発達障害(LD=学習障害、ADHD=注意欠陥多動性障害、高機能自閉症=知的障害を伴わない自閉症など)の子どもを新たに特別な教育の対象に加えて発足しました。ところが実際には、政治の責任は放棄され、「既存の人的・物的資源」で対応するなどとして、必要な予算と人員は確保されませんでした。
そのため学校現場では大変深刻な問題が起きています。
支援も施設も不足 教育条件整備はまったなし
神辺町湯田小学校を視察しましたが、ここでは17人が特別支援学級に通っています。
ところが、低学年から高学年まで一つの学級に在籍しているため、先生の支援の手が回らず、大変な困難を抱えていました。そのためお母さん達が手助けを行いに、支援活動に参加していましたが、教室は狭いため、大人が入ると、息が詰まるほどの状態です。しかも、こうした特別支援教育に携わる教職員の労働条件は劣悪で、全国的に多くの健康被害が起きています。障害のある子どもの教育は、その子どもの成長・発達する権利を保障するためのものです。同時にそれは、障害のある人びとが社会の構成員として自分らしく生きていく権利を保障されるためにも不可欠です。